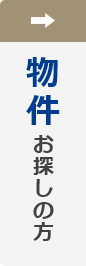「青森の不動産売却・買取・査定のコラム」の記事一覧(68件)
青森市・弘前市エリアの不動産売却・買取・査定に関するコラムです。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/02/22 09:39
契約と決済ってどう違うの?
Q.不動産の取引って契約と決済がありますよね。仮契約と本契約みたいなものですか。
A.いえ、そうではありません。あくまで不動産売買契約を締結したときが契約となります。 ただ不動産の取引では、契約と同時に物件を引き渡す等行うことができないケースが多く、それらを決済の際に行うことが一般的です。
Q.契約と引き渡しが同時にできないのは、どんなケースですか。
A.例えば、融資を利用する場合や居住中での売却、更地や測量してからの引き渡しの場合などです。融資を利用する場合、申し込みには契約書などが必要となります。居住中の場合や買い替えの場合、売却の契約の後に引っ越すことになります。さらに更地渡しですと、ここから解体作業や建物滅失登記が必要となります。
Q.確かにそうですね。
A.ですので金額はもちろん、残代金支払いや引き渡しの技術、引き渡しの条件など、特約条項を記した契約書を作成し、記名・押印することで売買契約を締結します。
Q.では、決済とはどんなことを行うんですか。
A.はい。残代金の支払い、所有権の移転登記です。通常、買主様が融資を受けられる金融機関で行うのが一般的です。買主様と売主様、不動産業者だけでなく司法書士が立ち会います。売主様から所有権移転登記に必要な書類や本人確認を司法書士が行い、問題がなければ融資の実行を行います。 動機に関する書類への記入以外、買主様は残代金や各清算金、仲介手数料、登記、火災保険に関する支払いの伝票の記載、売主様は買主様から頂く各代金の振込伝票、各領収書への記入などを行います。
Q.色々ありますね。
A.それらを手続きが終われば、鍵の引渡しを行います。 引き渡した鍵の本数、境界確認書や合意書などの書類の内容、引渡し日を記載した引渡し完了確認書を作成し署名・押印をいただきます。
Q.それでやっと終了ですか。
A. 売主様が住宅ローン利用していた場合には、抵当権の抹消が必要となります。 売主様は仲介担当者、司法書士と一緒に利用していた住宅ローンの銀行に行き、一括返済の手続きと抵当権抹消処理を取得します。売主様はここで手続き完了ですが、司法書士はここから法務局に行き抵当権の抹消、所有権移転、新たな抵当権の設定の登記申請を行います。
Q.決済ってそんなに多くのことをするんですか。大変ですねぇ。
A.抵当権の抹消書類は事前に手続きが必要ですし、印鑑証明書や住民票、戸籍の附票などの必要書類もあります。諸費用を含めトータルで必要な金額の明細もわからないですよね。 仲介の担当者は日々これらの業務を行っています。仲介手数料には、これらの手続きを安全に、スムーズに進めるための費用でもあります。
Q.なるほど、よくわかりました。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/02/21 11:33
古い家を高く売る方法ってあるの?
Q.古い家は売れるのでしょうか。
A.はい、もちろん大丈夫です。築年数が経った家でもリフォームや建替えをされる方もおられますので問題ありません。
Q.そうですか。知り合いから古い家の場合は、更地にしたほうが高く売れると言われたのですが、本当でしょうか。
A.はい、それは本当です。更地にして売り出した場合、土地の用途が広がって購入希望者様が増えることが多いです。その結果高く売れるケースもあります。また建物を所有しなくなった場合、空き家が残っていた場合に起こる倒壊や放火の心配もなくなりますので、売主様も安心ですよね。
Q.わかりました。ちなみに、更地で売却する際に注意することはあるのでしょうか。
A.はい、あります。更地にして売却する場合3つご注意ください。1つ目、家などの解体費を出す必要があります。2つ目、固定資産税の軽減がなくなります。3つ目、隣の土地の所有者と打ち合わせが必要となります。以上の3つです。
Q.詳しく教えてもらえますか。
A.はい、まず1つ目の解体費用は、現存の建物を取り壊す費用です。数十万から数百万かかる場合があります。続いて2つ目ですが、土地はと建物を所有していると固定資産税がかかりますが、居住用の宅地において200平米以下の部分は、課税標準額が6分の1になるという軽減措置があります。建物を取り壊した場合、この軽減措置が受けられなくなります。最後に3つ目。建物を取り壊す際に、隣の土地の所有者と話し合いが必要になりますので注意が必要です。
Q.更地にして売った方が良いのは分かりましたが、現場で売った方が良い場合はあるんでしょうか。
A. はい、その場合もあります。
Q.それはどんな場合でしょうか。
A.はい、更地にせずそのまま売却したほうが良いのは5つあります。
Q.詳しく教えていただけますか。
A.はい、まずは1つ目。建物がまだ利用できるビルやRC造などの場合です。2つ目。古民家など古いことに価値がある物件の場合です。3つ目。解体が困難な場合です。例えば足場を組む場所がないなどです。4つ目。解体費用が著しく高い場合です。最後に5つ目。手元に解体費用がない場合などです。 このような項目に該当する場合には、現状のまま売却された方が良いかもしれませんね。
Q.わかりました。まずは自宅の状況を確認してみます。
A.はい、その方が良いですね。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/02/18 10:26
不動産売却はどの様に進めていくの?
Q.自宅を売却しようと考えているのですが、どのように進めたら良いでしょうか?
A.ご売却の事情やスケジュールによって売却の進め方が少し変わってくることもありますので、まずは不動産会社にご相談ください。住宅ローンの残りがあるのか諸費用としてどれくらいかかるのか、その他にもその方に合ったサービスのご提案をさせていただきます。
Q.なるほど、査定額を出していただくのは次のステップになるのですか?
A.はい、近年では一括査定サイトをご利用になる方も多く、最初のご相談と査定額のご提案が同じタイミングになることも増えておりますが、ご相談を頂いた後に査定をさせていただくことになります。
Q.査定額はどれくらいで分かるのですか?
A.早ければご依頼を頂いた当日にもお伝えすることができます。よくご質問を頂くのですが、査定額と実際の売り出し金額は別物になります。売り出し金額はこちらから提案させていただくこともありますが、最終的に決めていただくのは売主様になります。
Q.売り出し金額が決まったら販売スタートになるのですか?
A.金額ももちろん大事なのですが、ご事情に伴うスケジュールなども考慮してご売却を開始します。その際に媒介契約書という契約書を締結させていただきます。
Q.売却活動が始まったら何かしておくことはありますか?
A.はい、ご購入を検討されるお客様もおうちにいらっしゃいますので、現在お住まい中でしたらお部屋の掃除をしていただきたいです。また、検討される方は土日に限らず平日にもいらっしゃることがありますので、可能な限りご協力をいただければなと思います。
Q.どのような販売活動をされるのですか?
A.不動産ポータルサイトといわれる物件探しをする方がご利用になるサイトに登録したり、レインズという不動産会社が見ることのできるサイトに登録するなど、広く広告をさせていただくことが一般的です。またオープンハウスを開催しご検討されている方に直接ご来場いただくこともあります。ご事情によってはあまり大々的に広告を出してほしくないという場合にはご相談をいただければなと思います。
Q.結構多くの方が見に来られるのですか?
A.一概には何とも言えないです。競合となる近隣の物件、価格、市場の動向などによって異なります。尚、万一見学希望者が少なかった場合は金額の見直しをご相談させて頂くこともあります。これは安易に安くするというわけではなくできるだけ高くかつ早期に売るためだと思って頂ければと思います。
Q.購入希望者が現れたらどうするのですか?
A.その際は購入申込書という書面を提示させていただきます。売買金額や手付の金額、引渡し時期などをご確認いただき双方で合意に至ったら、売買契約に進みます。
Q.契約が進めば一段落ですかね?
A.いいえ、ここからが大事なところです。引渡し日までにお引越しを完了させるのと引き渡し決済のご準備もあります。買主様が住宅ローンを利用される場合、銀行からローンの承認を得られない場合は白紙解約となってしまうこともあります。また引き渡しの後も契約不適合責任という責任が一定期間残ります。
Q.それはまだまだ安心できないですね。
A.そうですね。最後までしっかりとサポートさせていただくのが私たちの役目ですのでご安心ください。
Q.わかりました。ありがとうございます。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/02/15 15:28
契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いは?
Q.瑕疵担保責任はよく聞くのですが、契約不適法責任って何ですか?
A.はい、まず瑕疵とは欠陥、不具合という意味ですが不動産取引においては購入段階では気付かず実際に住み始めてから発見されるような欠陥や不具合ことを指します。そのため隠れた瑕疵とも呼ばれます。 売買後に売主が知らなかった瑕疵が発見された場合に売主が責任を負う範囲や対応する期間も定めたものを瑕疵担保責任といいますが、2020年4月1日から法改正により契約不適合責任に変わりました。
Q.瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いはなんですか?
A.はい、瑕疵担保責任と契約適合責任の大きな違いとしては瑕疵担保責任では買主が請求できるのは契約解除と損害賠償の2つだけだったのに対し、契約不適合責任は追完請求代金減額請求、催告解除、無催告解除、損害賠償請求の5つの請求ができるようになったことが見受けられます。
Q.その5つの請求と言うと、どのような請求なんですか?
A.まず1つめの追完請求とは、契約内容と異なっている部分を買主が契約通りするように請求することです 民法改正前はまずは買主が瑕疵を知らなかったことを証明する必要がありましたが、契約不適合責任では契約内容と合っているか合っていないかが問題になるため買主は請求しやすくなりました。 なお、契約内容と異なったのを売った場合売主は落ち度がなくても追加請求されます。
Q.買主が請求できるかどうか、よりわかりやすくなったのですね。
A.そうですね、次に2つ目の代金減額請求とは、追完請求の補修を請求しても売主が修理しないとき、あるいは修理が不能である時に認められる権利です。 あくまでも追完請求がメインの請求であり、それがダメな場合には代金減額請求ができ ます。 但し明らかに直せないもの、あと離婚の追加が不能である時は買主は直ちに代金の減額請求をすることが定められます。 そして3つめの催告解除は追完請求をしたのにも関わらず売主がそれに応じない場合に買主が催告して解除できる権利です。 売主が追完請求に応じない場合、買主は代金減額請求と催告解除の2つの選択肢を持っていることになります。契約解除された場合、売主は買主に売買代金の返還をしなければなりません。
Q.買主が売主に対して取れる選択が増えたということですね。
A.そうですね。次に4つ目の無催告解除は契約不適合により、契約の目的を達しない時に行うことができます。 逆に言えば若干の不具合程度で契約の目的が達成できる場合は無催告解除は認められないということになります。 そして最後に5つ目の損害賠償請求は契約不適合があった場合、買主は損害賠償請求をする権利が認められます。 民法改正後、売主に落ち度や過失がない場合は売主は損害賠償義務を免れるということが明文化されました。
Q.買主は請求できることが増え、売主は責任が増えたということですね。
A.そうですね、また追完請求の時にお話ししたように瑕疵担保責任ではそもそも論として、瑕疵かどうか、というところを通るだけで大変な手間でしたが契約不適合責任であれば契約内容と一致しているかどうかというところがポイントになるので、問題の有無をはっきりさせやすくなりましたが、一方で不動産の不具合等が契約内容に記載されているならばその不具合について契約不適合を問うことはできません。 そのためしっかりと契約内容を吟味する必要があります。 また瑕疵担保責任と同じで契約不適合責任も任意規定なので、実際の契約の内容がどうなっているか、というところをしっかりと確認するところも重要になります。
Q.売る場合も買う場合もしっかりと売買契約書を確認することが大事ということですね。
A. そうですね。わからない事があれば営業担当者にしっかりとヒアリングしましょう。
Q.わかりました、ありがとうございました。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/01/24 09:24
相続時の3000万円、特別控除の要件は?
Q.相続した実家でも3000前の特別控除を機使えるって聞いたのですが。
A.はい、相続によって空き家になった不動産を相続された方が一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から3000万円を控除することができます。
Q.それは昔からあった制度ですか。
A.2016年4月1日の時限立法で、2023年12月31日までとなっております 最近の話なのですね、なぜ出来たのですか? 少子高齢化人口減少に伴って増加し続ける空き家を減らそう国策である、空き家等対策の推進に関する特別措置法の税制上の措置としてできたのです。
Q.空き家対策が目的なのですね。ではどんな用件があるのでしょうか?
A.特例の対象となる被相続人居住用家屋とは相続の開始の直前において被相続人の居住用に供されていた家屋で次の3つの要件すべてに当てはまるものをいいます。
1つ目が、昭和56年5月31日以前に建築されていること
2つ目が、区分所有建物登記がされている建物でないこと
3つ目が、相続開始の直前において被相続人以外に居住していた人がいなかったこととなります。
Q.昭和56年より以前の建物なのですね。
A.はい、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物を旧耐震基準というのですが、そちらが対象になります。周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空き家建物のうち4分の3が旧耐震基準の建物と言われています。これらの対策が前提のため、建築時期の制限が設けられております。
Q.区分所有建物というと?
A.建物の中で複数に区分され、各個が住居店舗事務所等の用途で構成されている建物のことでマンションなどがわかりやすいと思います。
Q.一人で居住していたものでないとダメなのですか?
A.他に居住している人がいると空き家ではないので対策の趣旨とは異なってきます。
Q.逆に老人ホームなどに入っていた場合などはどうなりますか?
A.老人ホーム等への入所直前まで居住していて要介護要支援認定を受け、老人ホーム等に入社し相続開始直前まで老人ホーム等に入所していた場合、要件を満たせば適用な対象となります。
Q.賃貸で貸していたりした場合はどうですか?
A.事業貸付居住の用に供されていないことという要件がありますので適用の対象にはなりません。またこれは相続後から売却までの間も同じ条件となっていますので注意が必要です。
Q.その要件を満たせば適用ですか?
A.いいえ、空き家対策と建て替え促進が趣旨ですので売主様が耐震基準に適合するよう耐震補強するか、建物を解体し更地にして引き渡す必要があります。
Q.たくさん要件がありますが、すべて満たしていれば何十年も前に相続した物件でもいいのですか?
A.いいえ、これは相続が発生してから3年を経過する日の属する12月31日までとなっています。そしてその期限が2023年の12月31日までとなっています。
Q.期限が限られているのですね。
A.はい、そうです。それ以外にも譲渡価格が1億円以下であったり、親子や夫婦など特別な関係がある人以外への譲渡という、さまざまな要件があり手続きや証明書類があり確定申告の必要があります。
Q.これはかなり難易度が高そうですね。
A.はい、相続登記には司法書士、建物滅失登記には土地家屋調査士、税金に関しては税理士解体には解体業者、様々な専門家との連携が必要となります。 飼い主様を探すだけでなく、これらを紹介してくれる不動産業者を探すことが重要になってくると思います。
Q.わかりました、ありがとうございます。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/10/12 13:51
住宅ローンの支払に困ったときは?
Q.住宅ローンが支払えない場合って多いんですか?
A.はい昨年の新型コロナウイルスの感染拡大により、返済が困難な方が増えています コロナ化に関係なく住宅ローンの破綻率は毎年2%と言われていて50人に1人は返済が混乱になると言われています。 最近ではコロナ化により、例年以上に支払いが難しくなっている方が、多くおられると思われます。
Q.では住宅ローンが支払えない場合に行ったほうが良いことってありますか?
A. はい、そうですね、まずは借り入れをしている金融機関に相談することをお勧めします。 金融機関は返済が困難になった場合支払い猶予などしてもらえる場合があります。 その他無駄な出費を減らすことや家族の協力を得て収入を確保することも大事なことかと思います。
Q.その他にありますか?
A.はい、公的な機関や税理士、会計士など専門家に相談することも一つの手です。 様々な国や地方自治体の支援サービスを教えてもらえる場合もあります。
Q.わかりました。逆にやってはいけないことはありますか?
A.はい、それはですね、一番やってはいけないことは放置することです。
Q.放置ですか、そんな方はいるのですか。
A. はい、意外と多くの方が支払わなくなるとそのまま放置してしまうケースがあります。
Q.なるほど放置してしまうと良くないのですか?
A.はい、よくないです。優遇金利の停止はもちろん最悪の場合不動産を競売にかけられてしまう場合もあります。その時は住んでいる家から引っ越しをしなければなりません。
Q.競売ですかそれは大変ですね。
A.はい、そうなんです。住む家がなくなってしまいますから。
Q.その他に何かありますか?
A.はい、他には借金を借金で返すことやハイリスクな投資、ギャンブルにお金をつぎ込むこと、副業など無理なバイトをされることもオススメはしません。
Q.わかりました。住宅ローンが支払えなくなった場合にはまずは放置せずに相談をしていこうと思います
A.はい、その方が良いと思います
Q.ありがとうございます。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/08/06 14:49
生産緑地問題って何ですか?
Q.生産緑地着指定されている土地を持っているのですがこのまま持っていても問題はありませんか?
A.はい生産緑地に指定されている土地の所有者は30年間の営農義務というものが化されておりまして農地として管理すること生産緑地でやることを掲示することを原則として建物を建てることが出来ないこととなっています。1991年から生産緑地の指定が始まり2022年には多くの土地が指定から30年を経過するために営農ゲームが解除されます。そのまま保有された場合生産緑地に指定されている期間は固定資産税が減税されているのですが、解除されるとその減税は受けられなくなり、これまでより固定資産税が高くなってしまい ます。現在はその土地で農業を営まれているのですか?
Q.いえ、少し野菜を育てている程度ですので早く売却したほうがよさそうですね
A.生産緑地に指定された土地は売却することができないため、今すぐに売却することはできないんです。生産緑地に指定されてから30年経過すると解除できますのでその後に売却することができるようになります。
Q.そうなんですね。私の土地以外にも近くに生産緑地になっている土地がいくつもあるのですが…。
A.生産緑地に指定されているのは明晰では全国で合計6.56万haと言われていて、3大都市圏特定しないだけで1.2万haとなっています。特定市内の生産緑紫の8割ほどが2022年に期限を迎え、指定の解除、土地の売却という話が多くなることが予測されています。生産緑地は500平米以上の土地ですので、土地は将来的にはマンションの供給が形になり周辺の不動産相場が下がるのではないかという懸念があります。
Q.そうすると私の土地も安くでしか売却できないかもしれませんね。
A.その可能性はあります。ですので2017年に生産緑地法が改正されて特定生産緑地として 税制優遇を10年間延長することができるようになりました。また2018年には生産緑地を第三者に貸すこともできるようになったり、農産物の直売所などの建築もできるようになりました。
Q.いろいろな選択肢があるんですね。もし売却する場合何かアドバイスをいただけますか?
A.そうですね一番は価格の下落が始まる前に売却するのか、様子を見るべきなのかを地元の信用できる不動産会社に相談していただくことです。そのエリアにどれほどの生産緑地があって、またどれぐらいの方が売却するかによって状況が変わっていきます。地元の不動産会社にご相談いただき状況を確認しながら、売却のタイミングをご相談いただければと思います。
Q.わかりました、ありがとうございました。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/07/25 17:59
空き家所有者に対する責任が厳しくなった?
Q.現在所有している空き家を管理するのが大変で、どのようにしたらいいかわからないんですが。
A.はい近年同じように悩まれている方が多く、誰にも使用されていない空き家が急増し、問題になっております。この問題を解消するべく空き家対策とか別措置法という精度が設定されました。
Q.空き家対策特別措置法って何ですか?
A.空き家対策特別措置法とは空き家により、景観が損なわれたり衛生面防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、2015年2月に全面施行された法律のことです。空き家対策特別措置法が施行されたことにより管理が適切に行われていないと思われる、空き家に対して自治体が調査した後問題があると判断された空き家においては特定空き家として指定し所有者に管理を行うよう指導したり、状況の改善を促したりできるようになりました。
Q.特定空き家に指定されたらどうなるんですか?
A.例えば建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたゴミのせい害獣が発生しているなど、空き家が原因で前の住環境の影響がある場合所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。空き家対策特別措置法では所有者の義務である空き家の適正管理をしない消費者に対して市町村が助言、指導、勧告といった行政指導そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。
Q.それは面倒ですね。もし無視していたらどうなるんですか?
A.所有している空き家が特定空き家として指定された後、指導を受けたにもかかわらず状況が改善されない場合、国から勧告が出され固定資産税の住宅用地特例から除外されることがありその場合税金の負担が重くなってしまうので、改善が難しい場合は空き家を解体するか可能であれば売却も含めて検討していただいた方がいいかもしれません。
Q.結構大変なんですね。空き家を所有している皆さんはどうされてるんでしょうか?
A.はい、一般的に修繕をして住まいとして使用するか、売却を検討されております、現在空き家の発生を抑制するために特例措置があり、空き家を相続した相続人が耐震リフォーム、または取り壊しを行った後にその家屋や敷地を譲渡した場合には譲渡に本来必要となる譲渡所得の金額から、3000万円を特別控除できる制度もありますのでまずは信頼のおける、不動産会社ご相談いただければと思います。
Q.わかりました、ありがとうございます
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/07/19 16:09
居住用財産の特別控除とは何ですか?
Q.マイホームを売却した時の税金って何か特例があるんですよね?
A.はい、売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は不動産譲渡所得税が課税すぁれますが、居住用財産の場合、売却していた譲渡所得から3000万円を控除することが出来る特例があります。
Q.3000万円ですか、それは大きいですね
A.はい、ですのでこの特別控除を受けるためにはさまざまな要件があります。
Q.では、その要件を教えてください。
A.はい、まずは自己が居住している、または住まなくなってから3年目の年末までに売却することです。
Q.では、住まなくなってから人に貸した場合どうなりますか?
A.はい、賃貸などで人に貸していた場合でも3年目の年末までの売却であれば適応できます。
Q.建物が古くなって解体した場合はどうですか
? A.取り壊した日から1年以内にその土地の売買契約を締結し、住まなくなった日から3年目の年末までに売却すれば適応が受けられます。ただし、建物がある場合とは異なり敷地を人に貸すと適応が受けられなくなってしまうので注意が必要です。
Qその不動産を所有していた期間は関係あるんですか?
A. 所有期間や短期や長期などの税率に関係しますが、所有期間を居住期間の適応に関係ありません。ただし、売却した年の前年、または全前年に同じ3000万特別控除、譲渡損失など繰り越し控除などを利用した場合は適応が受けられません。
Q.例えば、親族に売却した場合でも適応が受けられますか?
A.特別な相手に譲渡した場合は適応が受けられないことになっており、配偶者や血族などが該当するため、適応外となります。
Q.共有の名義だったら誰か一人が特例を受けるのですか?
A.共有名義の場合は所有者それぞれが3,000万円の特別控除を受けることができます。
Q.計算してみて3,000万円を控除して+が出なかったら手続きしなくてもいいんですかね?
A.いいえ、この特例を受けるためには確定申告をすることが必要です。
Q.かなりありがたい特例ですから忘れないようにしないといけませんね。
A.ただし買い替えで購入に住宅ローンを利用した場合この3,000万控除と住宅ローン控除はどちらかしか使えませんので注意が必要です。
Q.はい、他に注意点はありますか?
A.この特例を受ける事だけを目的として入居したが良い仮住まいなど、一時的な目的の入居も適応が除外とされています。不動産の担当者への相談だけじゃなく、税務署へ確認されることをお勧め致します。
Q.わかりました、ありがとうございます。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/07/08 13:09
どんなところに注意して依頼先を決めればいいの?
Q.現在、日本の不動産会社ってどのくらいあるんでしょうか?
A.はい、おおよそ12万業者ありますね
Q.12万?!そんなにあるんですか、実査どの会社にするか迷いそうですね
A.そうですね、ですが不動産の相談をする際に、いくつかチェックをしていただければ、ピッタリの会社が見つかると思いますよ。
Q.それは、どんな会社ですか?
A.はい、一口に不動産会社と言ってもいくつもの業態があります。売買、賃貸管理、分譲などさまざまです。不動産会社も専門分野がありますから、すべてに対応できるわけではありません。
Q.そうなんですね。では売買の相談をしたい時にはどの会社に相談したらいいですか?
A.そうですね、売買でも購入か売却かにもよりますね。
Q.それでは売買で購入する場合にはどうでしょうか?
A.はい、その場合であれば購入希望エリアで物件を多く扱っている会社が良いですね。またネットで物件掲載が1社しかない場合には売主から直接依頼をされていることも考えられますので、条件面で交渉しやすかったりします。
Q.では、売却を依頼するときはどうでしょうか?
A.はい、それでしたらその会社のホームページをチェックし経営理念や社員紹介などをしっかりされている会社はお客様対応をしっかりしている会社が多いですね。
Q.最近ではまとめて不動産会社へ依頼もできるサイトが増えていますがどうなんでしょうか?
A.はい、そうですね。簡単に依頼できるからこそ最低限、依頼される会社のホームページを確認する必要があるかと思います。
Q他にチェックすることはありますか?
A.はい、最近では売却専用のホームページがある会社が増えています。売却方法や実績などを掲載されている場合もありますので役に立ちます。また、そのような会社は売却に慣れているので安心して相談することができると思います。
Q.不動産会社のホームページはしっかりチェックしたことがなかったので、次回は確認してみようと思います。
A.はい、その方が良いですね。
Q.わかりました、他にはありますか?
A.はい、仲介手数料無料をうたう会社は注意が必要です。不動産という大きな買い物で手数料を無料にするのには相応の理由があります。安易に契約せずなぜ無料なのか、担当者に聞いた方が良いですね。
Q.仲介手数料無料や半額ってよく見かけますが、すべて疑った方が良いですか?
A.はい、売買の場合には引き渡し後も関係性は続いていきます。すべてではないですが、手数料無料では誠実に対応しない会社も多いので、気を付けていただきたいと思います。
Q.わかりました、ありがとうございます。